2025-5-31
研究が進む量子コンピュータの活用。
世界で高速通信網の整備が進み、取り扱うデータ量は飛躍的に増え続けている。プログラムも複雑化する中、実用化が期待されているのが「量子コンピュータ」だ。現在のコンピュータでは不可能な同時処理により、スーパーコンピュータを凌ぐ計算速度が実現可能だという。実用モデルの完成は2030年代と予想されながらも、既に金融や研究など各分野での活用が始まっている。

量子コンピュータとは
量子コンピュータは量子力学の原理を情報処理に応用した技術を指す。原子や電子など、物質を構成する「量子」が持つ性質を利用することで、従来のコンピュータが不得意とする並列処理が可能になる。その計算速度はスーパーコンピュータの1億倍とも言われており、気象予測や創薬、金融市場分析、物流最適化など多方面での活用が期待されている。内閣府も2022年4月に「量子未来社会ビジョン」を策定し、量子コンピュータの研究・発展に向けて取り組む姿勢を見せる。
2016年以降、世界各地で進む開発
1980年代に理論が発表された量子コンピュータは、世界各地の研究室でハードの開発が進められ、2016年に第1号機が米国のIBM社からインターネットを通じて公開された。2019年以降は世界各地で200社余りの企業が開発に乗り出している。日本では、2023年3月に国産初の量子コンピュータが理化学研究所で稼働を開始したのを皮切りに、富士通、大阪大学でも稼働を開始した。量子コンピュータには量子状態の実現方法の違いによりイオントラップ方式、超電導方式、光方式、ダイヤモンドスピン方式などさまざまな方式があるが、2024年の時点では超低温下で計算を行う超電導方式が優位に立ち、2023年に日本で稼働した3台も超電導方式を採用している。
各分野が活用を開始
量子コンピュータがスーパーコンピュータの能力を超えるためには、情報の最小単位である「量子ビット」数が100万以上必要だとされる。現在開発中のハードは最大でも1,000ビット程度で、実用モデルの完成は2030年頃になるだろうと予想されてきた。
国産量子コンピュータの公開後、国内でも共同研究などの形で外部の利用が進んでおり、2025年にはNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)で国内公的機関として初となる量子コンピュータの利活用事例集を公開。同報告書によると、量子コンピュータの活用は「CAE分野」「AI分野」「セキュリティ分野」の技術のみならず、「製造分野」「交通分野」「エネルギー分野」「創薬・医療分野」「金融分野」といった産業界でも活用されると予想され、その裾野は計56事例に及ぶ。
ビックデータの活用に力を発揮
活用事例ではビックデータを分析・活用する取り組みが特に目を引く。例えば創薬医療の領域では、研究開発期間の短縮や新規の素材・創薬開発、製造・プロセス分野で研究開発の素材検索などが活用可能になるという。また交通分野では物流ルートや防災のルート最適化、エネルギー分野では発電・送配電計画、電力消費計画の最適化、その他にも金融関連でポートフォリオの最適化や金融シミュレーションにも活用できるとされている。製造・組み立て分野に関しては従来のコンピュータとの優位性は明確になっていないが、製造シフトの作成など活用できる業務は多岐にわたるだろう。膨大な組み合わせの中から最適な答えを探し出すタスクが、現在の量子コンピュータが力を発揮する業務と言えそうだ。
リスクヘッジと共に発展する技術
そんな中、量子コンピュータの普及に先駆けて、世界各国が取り組みを強める分野がある。それは「耐量子計算機暗号」と呼ばれる情報セキュリティ技術だ。演算速度の高速化に伴い、従来の暗号技術が解析されるリスクが高まるためだ。金融庁をはじめ警鐘を鳴らす声は多く、国内でもNTTなど各社が実証実験を行っている。
2025年には、理化学研究所とイオントラップ型量子コンピュータと既存のスーパーコンピュータ「富岳」との連携運用がスタート。国の研究機関である分子科学研究所や日立製作所も「中性原子方式」と呼ばれる新たな量子コンピュータを設置する予定を立てている。海外ではマイクロソフトやGoogleなど巨大I T企業も開発に力を入れており、おそらく各国の競争は今後も激化していくことだろう。近い将来、量子コンピュータの技術開発が更なる発展を遂げ、私たちの暮らしをより良くしていく新たな文明が生まれることを切に期待したいものだ。
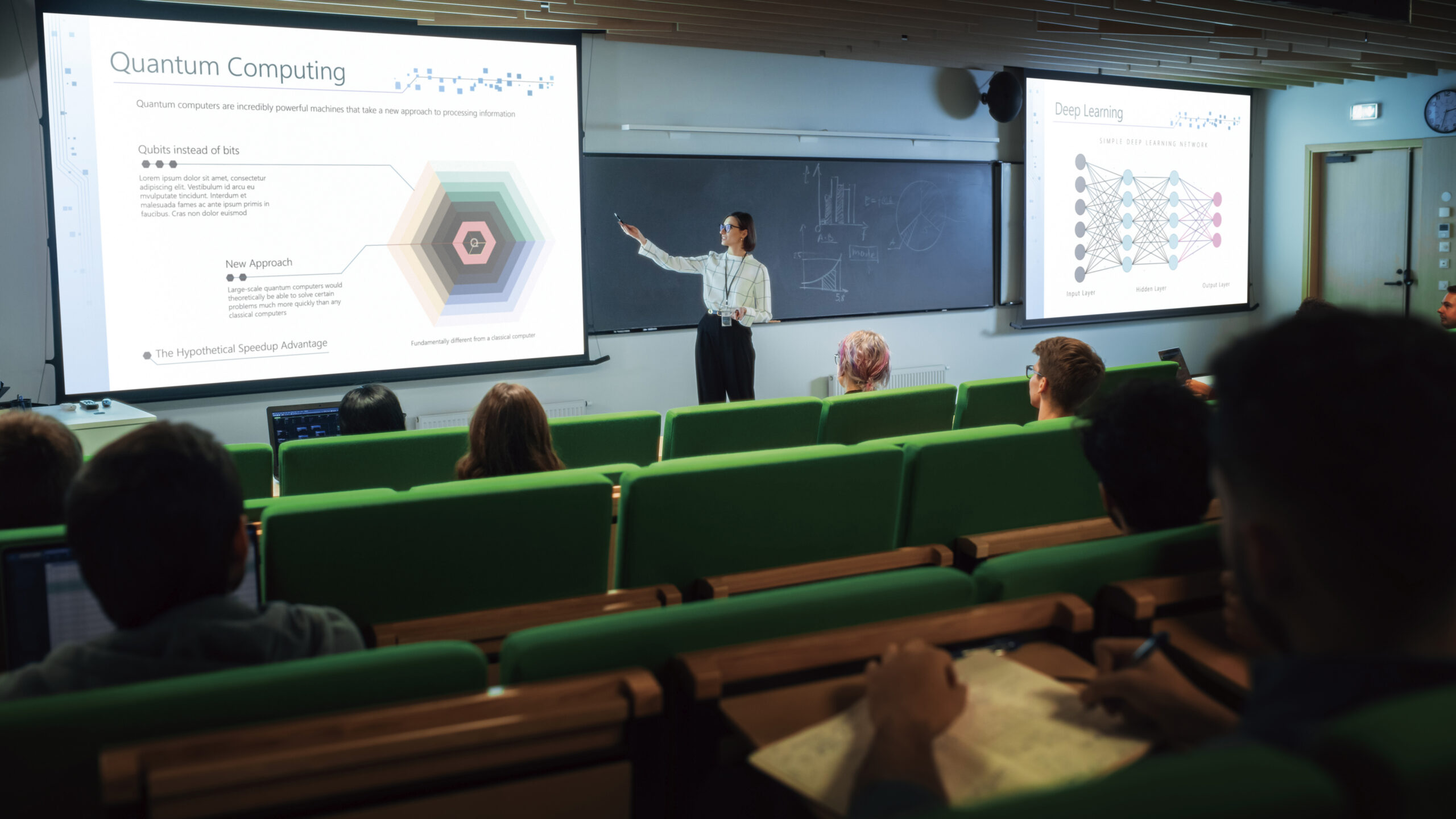
![Qualitas [クオリタス] ロゴ](https://www.qualitas-web.com/wp/wp-content/themes/qualitas/assets/img/site/logo.png)